弊社のようにファックスが主流の業界や、ペーパーレス化を考えているが方法やメリットがよくわからないという方のご参考になれば幸いです。
弊社製本事業の営業部では、昨年2020年4月に第1回目の緊急事態宣言の発令に合わせて、他部門に先駆けてペーパーレス化と社内文書の電子保存を決定しました。
ペーパーレス化のために便利なツールを取り入れ、営業部内でルールを決めてシステム化し、およそ1か月かけてそれまで膨大な紙で日頃業務を行っていたことをやめました。
ペーパーレス化を決めた主な理由は2点あり、・緊急事態宣言によって早急にテレワークに対応できる職場環境づくりを進めなければいけなかったこと、また・電子帳簿保存法改正など国が電子での保管や業務を推進していたことが挙げられます。
目次
経営計画書テンプレートを無料ダウンロード
すぐに使える経営計画書テンプレートをご用意しています。
年間1000社以上が活用し、経営理念、数値目標、行動計画が書きやすいフォーマットで、初心者でも安心です。
ペーパーレス化した目的
具体的に紙での管理をやめてペーパーレス化した書類は、お客様からの注文書、現場への仕様書、納品指示、請求書類などです。
そもそもペーパーレス化を営業部内で決めたのには、やりたくて行ったというよりも社会の変化の中でやらなければならなかったということが大きいです。そのためなるべく時間をかけずにかつみんなの業務がより効率化するようにという点が意識されました。
先ほども述べましたが、主な理由は2点あります
- 緊急事態宣言によって早急にテレワークに対応できる職場環境づくりを進めなければいけなかった
- 電子帳簿保存法改正など国が電子での保管や業務を推進していた
電子帳簿保存法の改正によって、2022年1月から税務署への事前申請が不要になったり、更に要件が緩和されるようになります。
この業界は、ファックスでのやりとりが主流です。なので、お客様や取引先にファックスをやめるということは言えません。
そのため、送られてきたファックスを社外でも誰もが瞬時に確認出来て処理できる環境づくりがまず大事でした。
ペーパーレス化のために採用した6つのツール
ペーパーレス化を実現するためにはいくつかツールを使うことをおすすめします。
1.iPadの活用
弊社では、ずっと以前から1人1台iPadを支給しています。
これは、営業も現場もデジタル化・IT化を推進し、コスト削減や生産性の向上を目的としたものでした。
手元に紙を持っている感覚でiPadを持っているので、現場の生産進捗状況や入荷状況、予定の受注状況などがすぐに確認できるようになっています。
これがペーパーレス化との相性が非常に良かったため、手元で電子書類やメール、チャット、さまざまな情報を常にみられる状態にあり、書類の処理や発信などを行うことができます。
2.メールFAX、インターネットFAX
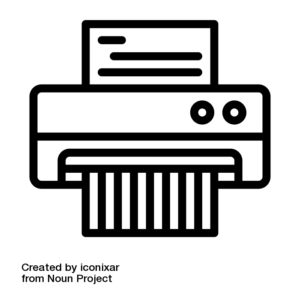
まず弊社で最初に入れたものは、メールFAX・インターネットFAXと呼ばれるものです。
どういうものかというと、ファックスを紙ではなくメールで画像データとして受信するシステムです。
これは非常に便利で、お客様から「ファックス送りましたので確認お願いします」と言われてもそれまでは会社に戻らないと確認できませんでした。
これが、社外からでもメールを見れば誰からいつファックスが来たかすぐにわかります。
1日に送られてくるファックスは100枚を超えることもあるので、普通にメール受信するとメールの量がすごくなります。
そこでファックス用のメールアドレスはファックス用のフォルダに分けて送られるように設定することをおすすめします。膨大な紙の削減にもつながりました。
3.Adobe Acrobat Pro DC
これは、PDFの作成や編集を行うのに非常に便利なツールです。
ファックスは、メールFAXを使うとPDFで受信することになります。
紙で処理を行っていたときは、書類に書き込んだりホッチキスでまとめたりする必要がありました。
これをPDF上で行うためには、PDF編集ツールが必要になります。その中でもAdobe Acrobat Pro DCが一番使いやすかったので弊社ではこれを使用しています。
文字を読み込んだり書き込んだり、複数のPDFをまとめたり差し替えたりなどの動作が直感でわかるようになっているのもよかったです。
4.クラウド請求書保管
膨大な紙を電子ファイルにしたことで、社内はかなりスッキリしました。
棚に大量にかさばっていたファイル類や机に広がっていた紙が一気になくなったためです。
代わりにパソコンの中には、大量の書類データが保管されることになります。大抵の書類は、そのままエクスプローラーや社内のサーバーに整理されて保管されているのですが、次の4種類の書類はタイムスタンプを押せるようツールが必要でした。
- 帳簿
- 決算書類
- 取引関係書類
- 電子取引
そこで、クラウド請求書保管のサービスを利用し、上記のような書類はすべてそこのクラウド上で保管しています。
5.生産管理システム
実質これなしでは、営業部のペーパーレス化がスムーズに実現することはなかったといっても過言ではないのですが、社内システムです。
お客様からの注文書や指示書、現場への仕様書や納品指示などのPDFはすべてこのシステム内で管理され、製造現場と生産管理と営業が共有してすべての情報を見ることができるようになっています。
- 仕様書、注文書の管理
- 生産管理一覧表の自動作成と管理
- 各工程の日報作成とCSVデータのダウンロード
- 各工程の品質チェック表管理
- 入荷伝票、出荷伝票の作成及び保管
- 各工程の製品を識別する荷札作成
- 加工予定表の自動作成と管理
- 外注管理一覧表の自動作成と管理
- 納品予定一覧表の自動作成と管理
- 未入荷部材の検索
- 商品別ABC分析表の自動作成
日付ごと、お客様ごと、さまざまな検索方法で見ることができ、製造現場のペーパーレス化もこのシステムによって実現しています。印刷・製本業界に限らず、他社様にも紹介させていただいています。
気になる方はご紹介もしていますのでご連絡ください。
6.MetaMoji Share
これは、PDFを共有して編集できるサービスで、会議などに使用しています。
みんなが集まって同じ書類を見て会議をする、といったことがテレワークによってZOOMなどを使用して行うことが増えました。
そんなとき、手元にiPadやPCで書類を共有して書き込むことができるので(自分だけで見たり、発表者だけが書き込んでいるのを見たりできる)便利でした。
ペーパーレス化で苦労したこと
ペーパーレス化にあたって一番苦労したことは以下の点です。
どういったルールで管理するのか
各営業担当者で、まったく書類の管理方法が違ったため、どんな書類があるのか、どのような処理が必要なのか、それらをどうすれば全員が統一したルールで管理できるのか。といったことが、ペーパーレス化するにあたって非常に困難でした。
これにあたっては、PCの扱いに長けたメンバーを中心に、一番手順がシステム化されていた担当の業務をまずは完全ペーパーレス化することで、問題点をその都度洗い出し、ルールを整え、それをすべての担当者にも適用することで、全メンバーがほぼ同一の処理方法で書類を処理することができるようになりました。
具体的には、「フォルダは、各お客様ごとのフォルダに分けたうえで、その中に注文書、仕様書、納品指示、請求書の4つを作成する」「書類のファイル名を【1007(納品日)_●●●(品名)】みたいに納品日を基準に日付を先頭につけて管理する。」「不要なものは削除する」を徹底しました。
必要・不必要な書類が混在
必要な書類・不必要な書類が混在して保管されていたことです。
単にそのままスキャンするのではなく、書類の内容を精査して残すか否かの判断をするところから始めなければなりませんでしたが、担当者ごとに把握している情報も異なるため、その識別にかなりの時間を要しました。
しかしながら、その工程を辿ることによって、必要のない文書のために今までいかに無駄なスペースを使っていたか、また自分たちがどれだけ情報の取捨選択に鈍感であったかに気づくことができました。
不要な情報を取っておくということは、必要な情報を見つけにくくするということでもあります。
そのことが各担当者の担当外の情報への認識の薄さにも繋がっていたのだと理解いたしました。
必要なものだけをデータ化し誰にでも見えるように共有するペーパーレス化という取り組みは、紙そのものだけではなく不要な情報のレス化でもあるのだと感じました。
ペーパーレス化で起きた3つの変化
ペーパーレス化をして、営業部の業務の仕方や時間のかけ方が大きく変化しました。
慣れていたことを変えなければいけない・ツールにお金がかかるといったデメリット以上に、ペーパーレス化を実現したメリットが大きかったです。
①情報の取捨選択と書類検索の速度
ペーパーレス化に伴い、不要な書類を無くしました。そして、不要になって保管する必要のないものは削除するルールを徹底しました。
それによってまず、営業部員が業務の中で情報の取捨選択を考えるようになりました。
また以前は、お客様からの書類が更新された場合、元の書類を探すためにいちいちファイルを取り出し、記憶を頼りに紙をめくることで古い書類を探して差し替えていました。
書類を電子化してからは、必要な書類の【受注番号】や【品名】、【納期】で検索をかければ、必要な書類が一瞬で見つかるようになり、事務作業の効率が大幅アップしました。
②営業部内で書類を共有化
書類の保管方法やファイル名を共通化したことによって、担当のお客様以外でもどこにどんな書類があるのかがわかるようになりました。
書類をデータで共有できるので、1社のお客様に対し、複数名で対応できるようになり、ダブルキャスト化やジョブローテーションがスムーズになりました
③テレワークを実行できるようになった
書類をクラウド上に保管し共有することで、いつでも誰でも、さらにどこででもデータにアクセスすることができるようになりました。
そのため、コロナの拡大に限らず従業員の働き方によっても会社で必ずしも仕事をしなければいけないということはなくなります。小さなお子さんをもつ従業員もいるため、「家でも仕事ができる」というのは会社・社員の双方にとって大きな利益になります。
実際に、弊社の従業員は現在もコロナ以降、テレワークをメインにし月に1,2度のみ会社に出社するという方もいます。
今後の展開
★今後の展開ですが、
全書類のペーパーレス化に成功したので、さらに発展させ、情報の共有化をより深く進めていくことで、担当者ごとの認知の垣根をなくし、実務の完全ダブルキャスト化、ひいては全員がどの担当者の業務でも問題なく処理できるような環境・仕組みを作っていければと思っております。
経営計画書づくりを、迷わず進める
経営計画書の使い方から、数値目標・行動計画の落とし込みまで。
経営者の疑問やお悩みを解決する Zoomオンラインセミナーを開催しています。
経営計画書を初めて作る経営者向けに、
セミナー後すぐ、次にやるべきことが明確になる内容です。
- 経営計画書がなぜ必要なのか、目的の整理
- 経営計画書で、銀行を味方につけるためのポイント
- 数字・方針・行動計画をどうつなげるのか
- 初めて作る際につまずきやすいポイント
開催日時
- 1/28(水) 10:00–12:00(Zoom)
- 2/4(水) 10:00–12:00(Zoom)
- 2/16(月) 10:00–12:00(Zoom)
- 2/25(水) 10:00–12:00(Zoom)
- 3/4(水) 10:00–12:00(Zoom)

