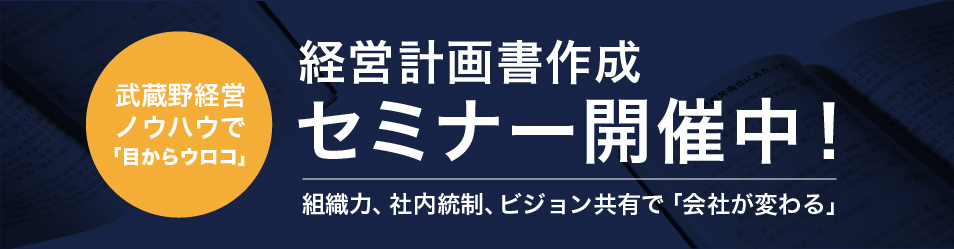経営計画書作成について、「作成・更新が負担」「社員になかなか浸透しない」「計画通りに仕事が進まない」という課題をよく耳にします。
そんな経営者の方でも、セミナーを受けていただいたことで「作成のためにやるべきことが見えてきた」「そんな使い方があるのか」といった経営計画書作成について前向きなお声を多くいただいております。
経営計画書は、作って終わり、ではありません。作成したその先にこそ価値があります。
企業の経営力・マネジメント力を強くしたい、売上を向上させたい、社員が働きやすく辞めない組織作りをしたい、そんな目標達成のための経営の道具として欠かせないものとなります。
経営計画書を作ることを目的にしてしまい、その先にどう活用していけば良いかわからない経営者の方のご参考にしていただければと思います。
目次
経営計画書テンプレートを無料ダウンロード
すぐに使える経営計画書テンプレートをご用意しています。
年間1000社以上が活用し、経営理念、数値目標、行動計画が書きやすいフォーマットで、初心者でも安心です。
1.なぜ経営計画書を使うのか、を知る
経営計画書は、会社が計画的に経営を推進し、目標とする成果をあげるためのものです。
単に理想の数字を並べたものではなく、その目標を達成するための具体的な戦略・戦術・戦法を明示しなければならなりません。そして、その進捗状況を随時確認・管理することで、場当たり的な対応から脱却し、経営の羅針盤として経営を進めていくことができます。
誰のための経営計画書か
経営計画書は、誰のために作成するのでしょうか。
経営者自身のためであり、従業員のためであり、金融機関など社外の人のためでもあります。
つまり「経営に関わる全ての人」と言うこともできます。
企業が存続・発展していくためには、企業が将来目指すべき目標を明確にし、それを具体的に数値化し、ヒト・モノ・カネの経営資源をいかに適切に調達・配分するかを適切に計画する必要があります。
この計画を着実に実行することが、安定した成長の条件となります。
経営計画の進捗状況は、自社の従業員だけでなく、取引先や金融機関などにも開示し、理解を得る必要があります。
経営計画の着実な進捗を公表する活動は、会社が健全であることを内外に証明し、会社の経営環境をより好ましいものへと変化させるものとなります。
課題解決のヒントになる
経営計画作成の最初の荒削りなステップは、経営トップと全従業員の将来の「夢」を描くことです。
この段階では、現実の延長線上にあるものではなく、希望を抱かせ、何としても実現したいとの思いを抱かせるような理想像を描くことが重要になります。
これがビジョンです。
具体的には、経営理念や経営方針を再確認し、近未来の市場動向を分析し、強化すべき事業領域を想定します。
そして、その事業領域で生き残るために必要な会社の経営力を整理・検討します。
ここで、会社のあるべき姿の「夢」が明確になり、それを具体的な数値目標に落とし込んでいくのです。
理想像と現実を対比させると、大きなギャップがあることに気づきます。
将来目指すものを獲得しうる経営力と現状を比較してギャップを導き出すことで、現在抱えている問題や課題が明確になります。
これらの問題や課題を解決するための具体的なアクションプランが、経営計画の詳細な内容になります。
社長と社員が同じビジョンに向かって進む
つまり、経営計画書の作成することで、社員が経営者の目指しているものを明確に理解することができます。
経営計画書には、その企業が目指す未来が描かれており、その企業と関わることで、どんな良い未来が待っているのか、関係者全員が想像しやすくなります。
そのために中小企業が抱える課題の根本原因である「コミュニケーション不足」の解決につながるのです。
2.経営の道具として使いこなす
社員は基本的に価値観がバラバラです。
経営方針があっても、それを社員に粘り強く説明しない限り、浸透させることはできません。機会があるごとに経営方針を直接社員に説明しています。
経営方針は必ず明文化すること。
ビジネスでよくあるように、経営方針が口頭を通じて社員に伝えられると、「伝言ゲーム」のようなニュアンスで末端の社員まで伝わってしまうことがあります。
現場の論理でニュアンスを変えることもよくありますが、それではダメなんです。
トップの考えを文書化し、全社員に正しく伝える努力が必要です。
株式会社MOTOMURAでの活用方法
当社では経営計画書をどのように活用しているかを紹介します。
勉強会で経営計画書に書かれた方針を全員で声を出して読み、一つずつ解説しています。この後、40分くらいかけて方針を解説し、最後に全員が勉強になったことや、これからの仕事に生かせそうなことについて所感を述べます。

この勉強会は「早朝勉強会」と呼び、始業の1時間前に行っています。始業前に始めるため、必ず時間外手当を支給しています。方針は社員に定着するだけでなく、着実に実行してくれる組織に生まれ変わります。
経営計画書発表会を実施する
経営計画書を仏とするなら経営計画発表会は魂を入れる儀式であり、金融機関を味方にする最高の場になります。
経営計画書を作った社長は、社員、金融機関、来賓の前で、自分の声と自分の言葉で方針や数字について解説する(=魂を吹き込む)儀式を執り行う。
この儀式が経営計画発表会です。
3.融資を引き出す道具として使いこなす
経営計画書は社員に向けたものであると同時に、金融機関に対しても示すものです。
企業の成長に欠かせない融資の可否は、どのように会社の将来性をアピールできるかにかかっています。ところが、金融機関に経営計画書を配布していない会社はけっこうあります。宝の持ち腐れと言っても過言ではありません。
ぜひ融資を引き出す道具として活用しましょう。
活用の仕方のポイントは3つです。
- 経営計画発表会に金融機関を招待する
- 経営計画書ができたらすぐに金融機関に届ける
- 金融機関を定期訪問し、経営計画書を使い近況報告を行う
経営計画書を持っていることは、金融機関にとって信用力を増やすことにもなります。
融資を引き出す道具として、経営計画書を最大限に使いこなしましょう。
7日間で成果の出る経営計画書を完成させる
現場改善や業務改善、人材採用・育成など、あらゆる業種・業態に役立つノウハウが経営計画書には盛り込まれているため、継続的に成果を出すことができます。
経営計画書でどのような課題が解決できるのか、どの様なポイントで経営計画書を作ったらいいのか?
1Dayスクールでは、経営者が知っておきたいその仕組みをお伝えしています。
経営計画書の作成にお悩みの方に大変ご好評をいただいております。
経営計画書づくりを、迷わず進める
経営計画書の使い方から、数値目標・行動計画の落とし込みまで。
経営者の疑問やお悩みを解決する Zoomオンラインセミナーを開催しています。
経営計画書を初めて作る経営者向けに、
セミナー後すぐ、次にやるべきことが明確になる内容です。
- 経営計画書がなぜ必要なのか、目的の整理
- 経営計画書で、銀行を味方につけるためのポイント
- 数字・方針・行動計画をどうつなげるのか
- 初めて作る際につまずきやすいポイント
開催日時
- 1/28(水) 10:00–12:00(Zoom)
- 2/4(水) 10:00–12:00(Zoom)
- 2/16(月) 10:00–12:00(Zoom)
- 2/25(水) 10:00–12:00(Zoom)
- 3/4(水) 10:00–12:00(Zoom)